相関関係と因果関係correlation and causation
(目次)
1. 相関関係と因果関係とは
2. 相関関係
3. 因果関係
4. 擬似相関
5. 因果関係の判定
1. 相関関係と因果関係とは
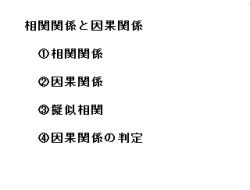
(解説)
1.相関関係と因果関係について、説明して行きます。
2.相関関係が有っても、因果関係が有るとは限り
ません。
3.相関関係は、因果関係の前提条件となります。
4.逆に言うと、相関関係が無い場合は、因果関係は
有りません。
5.数学記号で示すと、下記の様になります。
因果関係 ∈ 相関関係
2. 相関関係
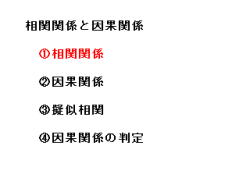
(解説)
1.相関関係ついて、説明して行きます。
2.相関関係とは、説明変数xと目的変数yの線形関係
を意味します。
3.相関関係は、相関係数rと言う指標で表されます。
4.相関係数rは、−1から1までの値を取ります。
正の相関: 0 < r ≦ 1
負の相関: −1 ≦ r < 0
5.ここで注意して欲しい事は、相関関係は線形関係の
有無であることです。即ち、理論や法則などは考慮
していません。
3. 因果関係
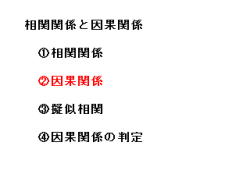
(解説)
1.因果関係について、説明して行きます。
2.因果関係とは、原因と結果の間に理論や法則が有る
事を示しています。
3.水道の例で説明して行きます。水道は蛇口を捻ると
水が出ます。
4.これは、以下の様な関係です。
蛇口を開く → 弁が開く → 水が出る
5.上記の様に、理論や法則が有る事が前提です。
4. 擬似相関
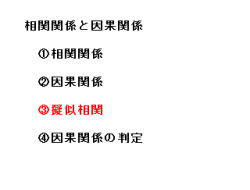
(解説)
1.擬似相関について、説明して行きます。
2.擬似相関とは、原因と結果が関係して見える事で、
実際には関係が無い場合です。
3.血圧と年収の例で説明して行きます。ある統計では
血圧が上がると年収も上がると言うデータが有り
ました。
4.理論的には上記のデータには、根拠が有りません。
5.色々と調べると、血圧と年収に共通する第三の因子
として、年齢がある事が判明しました。
6.年功序列賃金では、上記の現象が発生します。
5. 因果関係の判定
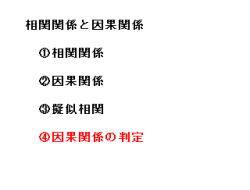
(解説)
1.因果関係の判定について、説明して行きます。
2.因果関係を判定する方法は、原因と結果の間に理論
や法則が有るかどうかを調べる事です。
3.理論や法則を考えるには、色々な角度から物事を
客観的に見る事が大切です。
4.最終的には、自分で推測する、過去の類似例を調べ
る、人の意見を聞くなどを行い決定します。
5.ただし因果関係の判定を行った後も、「判定結果の
可能性が有る。」程度に留める方が良いかも知れ
ません。
品質管理ソフトは、下記をクリックして下さい。
本館:エクセル将棋館(品質管理ソフト)